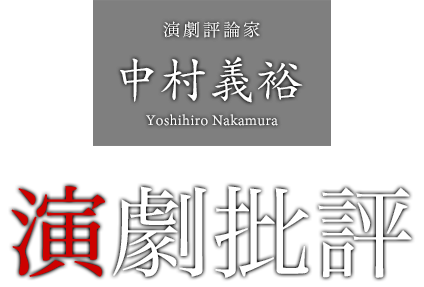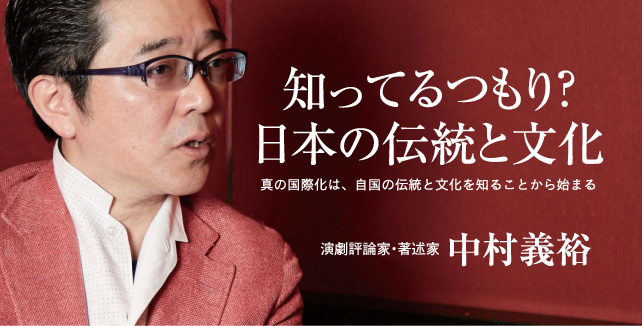ほとんどの場合、芝居のタイトルはその内容をある程度予想させるものだ。内容がわからないタイトルでは、観客の集客にも影響するし、観客も判断に困るからだ。しかし、美輪明宏へのオマージュである『MIWA』などのいくつかの例外を除いて、野田秀樹が創る芝居は、タイトルからではおよそ内容が予想できない。そればかりか、彼は観客に挑戦するかのように、プログラムにも、他の芝居のように「あらすじ」を載せていない。対談やコメントなどである程度の予想が付く場合もあるが、それもごく一部だ。
まるで、どこまで観客を裏切れるか、芝居の仕掛けに気付かせないようにするか、という「挑戦」を楽しんでいるかのようだ。 続きを読む
演劇批評
一覧 (12ページ目/全18ページ)
正月の歌舞伎座は、何とはなしに賑やかな風情が漂い、華やかな空気に包まれる。俳句の季語に「初芝居」とあるように、年が改まって華やか顔ぶれの役者と、賑やかな演目が揃うか
らだろう。今月も、ベテランから花形まで、多彩なメンバーで歌舞伎座の一年の幕が開いた。 続きを読む
「花より男子」
舞台もテレビも、漫画を原作にしたものが増えているのは昨今始まった風潮ではない。昨年も、『ワンピース』が歌舞伎化されて大きな話題になったのは周知の事実だ。この風潮を批判的な眼で眺める向きもあるが、私は、作品を厳選し、どう手を加えるかの問題に過ぎないと思っている。つまり、素材をどこに求めようと、出来上がった舞台の質が問題であり、その出来が悪かった時に、「原作が漫画では…」と言うのは卑怯な話だと考えている。ただ、芝居の制作現場において、すでに読者を多数獲得している実績のある漫画に頼りすぎるあまり、素材を吟味する作業がいささか疎かにされ、玉石混交になっている感があるのは否めない。 続きを読む
ギリシャ悲劇の『王女メディア』を1978年に平幹二朗が蜷川幸雄の演出、辻村寿三郎の衣装という異色の顔合わせで、日生劇場で初演をしてから38年が経った。その間、国内だけではなく、本国のギリシャはもとよりイタリア、フランス、アメリカ、カナダなどで上演を重ね、2012年には「一世一代」と銘打って全国各地50か所での公演を行った。しかし、その舞台が非常に優れていたために、昨年の9月、東京・立川を振り出しに、北海道から九州まで、今年の3月までかけて実に58か所で「一世一代、ふたたび」として12回目の公演を行っている。 続きを読む
師走の国立劇場で『東海道四谷怪談』を上演している。本来であれば、6月から9月辺りまでが「旬」のはずのこの作品を、なぜ真冬、それも暮れに、と思ったが、鶴屋南北がこの芝居を初演した時のことを想い出し、「暮れでなければ上演できない」方法での上演なのだ、と納得した。その関係をばらしてしまえば、「忠臣蔵」だ。歌舞伎の三大名作に数えられる『仮名手本忠臣蔵』をかなり意識した作者の南北は、登場人物のそれぞれに『忠臣蔵』との関わりを持たせたばかりではなく、初演の折は『四谷怪談』と『忠臣蔵』を交互に上演した記録がある。 続きを読む
「根岸庵」とは、俳人・正岡子規が東京での住まいとしていた場所で、「律」とは子規の妹のことだ。36歳で亡くなった子規とその家族、俳人の仲間を描いた小幡欣治の作品を、劇団民藝が上演している。この芝居は1998年に初演されたもので、その折は子規を伊藤孝雄、母・八重を北林谷栄、律を奈良岡朋子が演じ、作者はそれぞれの役者に「当て書き」をした形だった。今回は配役を一新し、丹野郁弓が演出して明治に燃え尽きた俳人と周りの人々の息遣いを炙り出した。 続きを読む
k
今年の顔見世は、「十一世市川團十郎五十年祭」でもある。神道の信仰が篤かった市川團十郎家・成田屋の、現・市川海老蔵の祖父に当たる十一世團十郎が没して半世紀。その舞台に、海老蔵の長男「堀越勸玄」が初御目見得として2歳数か月で舞台に登場する『江戸花成田面影』で、歌舞伎座は一気に温かな空気に包まれる。子役として特定の役を演じるわけではないため、「初舞台」ではなく本名での初お目見得になるが、故人の曾孫に当たり、最も若い世代の歌舞伎役者の誕生に、ご馳走で花を添えている坂田藤十郎、片岡仁左衛門、尾上菊五郎、中村梅玉らのベテランも、完全に喰われた格好だ。この坊やが、これからどういう道を歩むのかは誰にも判らない。しかし、新たな可能性の誕生であることは間違いない。海老蔵も完全に「父親の目」で初お目見えの子息をサポートする様子が微笑ましい。 続きを読む
戦後70年を機に「先の大戦」の際の、「いわゆる従軍慰安婦」の問題が誤報や虚報が入り乱れて話題になっているが、この物語はそれに遡ること40年、日露戦争前夜の1903年から1911年までシンガポールに置かれていた娼館の話だ。宮本研の作品を伊藤大が演出し、綱島郷太郎が演じる日本から若い女性を連れて来る女衒(ぜげん)・巻多賀次郎と、シンガポールへ連れて来られた女性たちの物語だ。 続きを読む
今月の顔見世興行で、市川海老蔵が大仏次郎の『若き日の信長』を演じている。この作品は、昭和27年に、海老蔵の祖父に当たる九世市川海老蔵(後の十一世市川團十郎)のために書かれたものだ。無法、放埓で知られた青年時代の織田信長の行動や思想を温かく肯定的な視線で捉えたものだ。海老蔵の父・十二世團十郎もこの役を演じており、祖父以来の当たり役と考えてもよいが、それが戦後の作品、というのが面白い。 続きを読む
森光子が、その女優人生を賭けて2017回にわたって演じた『放浪記』が、6年の歳月を経て、メンバーを一新し、北村文典の新しい演出でよみがえった。観客の中には、森光子の舞台がまだ鮮やかな人も多いだろうが、没後もこうして作品が受け継がれ、新しい生命を吹き込まれることを考えれば、日本の演劇の財産が残ったことになる。演出にも相当細かな検証の後が散見され、まず、全体のテンポが速くなった。以前の上演の折と比較をすると、休憩時間の短縮もあるが、全体で25分短くなり、3時間20分の上演時間である。細かな台詞をカットし、舞台転換の間に見せるスライドや文章も変わっている。人物の動きを大きくし、今までは動かずに芝居をしていた役に動きを与えるなど、全体的に躍動感のある舞台だ。
今回は、仲間由紀恵が林芙美子に挑戦。まだ、森光子の印象が強い中で、あえてこの役に挑戦する気概はたいしたもので、初演の割には良い出来だと言える。大詰の晩年の演技が年齢相応に老けられるか、と幕が開く前には危惧したが、そこも彼女の芝居で乗り切った。ともすれば、森光子が遺した大いなる遺産の芝居に引っ張られそうになる中で、懸命に「自分の林芙美子」を創ろうとする姿、好演である。林芙美子の強烈なまでの上昇志向と余りにも苛酷な人生が随所で感じられ、生々しい女性の姿が前面に出た。
今回の演出は、林芙美子という一人の女性の半世紀の側面と同時に、芙美子を囲む人々の人生をも同時に引っ張り出そうとする「群像劇」のような感覚がある。森光子の『放浪記』が苦難を乗り越えて栄光を勝ち取るまでの女性の半生記だとすれば、今回の『放浪記』は、大正末期から昭和にかけて、自分の可能性を信じて文学の世界で生きようとした若者たちの、辛く哀しい青春群像劇、と見ることもできる。作品の新しい解釈の一つであろう。
そのためか、芙美子のライバルである日夏京子(若村麻由美)、詩人の仲間の白坂五郎(羽場裕一)、アパートの住人で芙美子に好意を寄せる安岡(村田雄浩)、芙美子と一時結婚する詩人の福地貢(窪塚俊介)らが、芙美子の引き立て役に回るのではなく、程度の差はあれ苦悩を抱え、理想と現実のはざまに生きる人間としての実在感が増した。全員が初めて、という緊張感が巧く働いた部分もあるのだろう。
お金持ちのボンボンで、おっとりした雰囲気の白坂を演じる羽場裕一が良い。時折、以前演じた『マイ・フェア・レディ』のピッカリング大佐のような感覚がふと出て来るが、鷹揚とした感覚がはまり役だ。次いで、結核を病んでいる詩人の福地を演じている窪塚俊介も好演だ。ピリピリした病人の、狡猾さと嫉みがよく出ている。柄が役のイメージに似合っており、男の陰影が出た。以前は山本學が演じていた安岡が村田雄浩。最近、硬軟さまざまに役柄を広げているが、山本學とは違い、善意だけが前面に出ていないところにかえって人間臭さが感じられる。ライバルの日夏の若村麻由美、この役は、以前は奈良岡朋子が最も数多く演じ、池内淳子、黒柳徹子などが演じて来たが、そうした人ほどの強烈な個性はないのが残念だ。
仲間由紀恵が、この作品を森光子のように舞台のライフワークとすることができるかどうかは、今後の問題だろう。東京公演を終えた後、名古屋・大阪・福岡と、来年の1月末までこの芝居が続く。その過程でだんだんに練り上げられてゆくだろうが、少なくも、今後の再演を見据えた「覚悟」が見て取れた。この作品が、再演されるかどうか、は観客の評価次第だ。そこに仲間由紀恵の覚悟の結果が出るだろう。しかし、私はより練り上げての再演を観たい、と思う。
© 2026 演劇批評
Theme by Anders Noren — ページのトップへ ↑