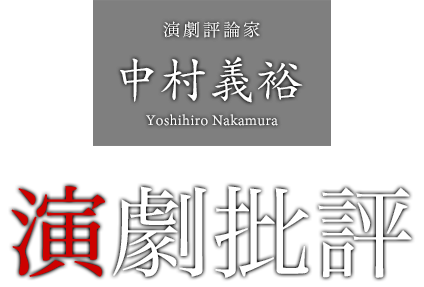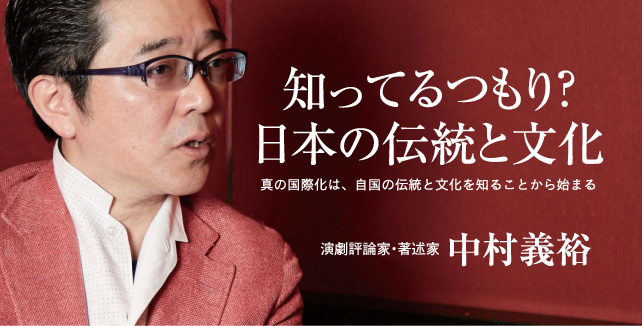今まで、八月公演だけしか行わなかった「三部制」を、試験的に他の月にも拡大したようで、今月は歌舞伎の「三大名作」の一つ、『義経千本櫻』を三部に分けて、通しに近い形で上演している。『義経千本櫻』であれば、平知盛、いがみの権太、佐藤忠信という三人の男を軸に据え、その運命を描くという考え方で場面を選べば、三部に分けて上演するには適切な名作だ。市川染五郎、市川猿之助が朝から夜まで大奮闘し、松本幸四郎が「上置き」の存在で第二部の「いがみの権太」を演じる、という構成も、観客の年代の広さに応えられる仕組みだ。三部に分けると、各部の上演時間が3時間程度で、従来の二部制の4時間~4時間半という上演時間に比べ、通常のストレート・プレイ一本分ですみ、一日がかりでなくとも歌舞伎が観られるのが何よりも気軽で良い。 続きを読む
演劇批評
一覧 (11ページ目/全18ページ)
架空の都市・フォーダムシティは、経済の中心地であると同時に、国内でも最も治安が悪く、麻薬の取引が横行している。市長のアルバートは裏社会の一掃を願い、敏腕の麻薬取締捜査官・ケントの協力を仰ぐものの、裏社会はマフィアの「コッピファミリー」に牛耳られている。そんな中、ストリートサーカスのチーム「ミラージュ」と出会ったケント、そしてケントを狙うコッピファミリーのスワン。やがて、「コッピファミリー」を追い詰めた「ミラージュ」のメンバーとケントが出会った相手は…。
ストーリーの展開だけを追っていけば、細かな点で綻びがあるのは否めない。しかし、この作品は、ストーリーの内容に感動することに第一点を置いたものではなく、「ダンス・ミュージカル」という形態で、歯切れよく展開するドラマとダンスをどう見せるか、に眼目が置かれている。 続きを読む
毎年五月に恒例の国立劇場公演、今年は「創立85周年」と銘打って、第三世代が中心となって34年ぶりに『東海道四谷怪談』を上演している。創立メンバーであり、当代の河原崎国太郎の祖父に当たる五世・国太郎の上演以来のことだ。今年、第二世代の筆頭である中村梅之助を喪い、劇団の精神的支柱となくすという大きなショックを受けたが、前進座育ちで退団後幅広い活動を見せる瀬川菊之丞を記念公演の客演に迎えての意欲的な上演となった。 続きを読む
今、「チャールズ・ディケンズ」という文豪の名を挙げた時に、我々の頭に即座に思い浮かぶのは『クリスマス・キャロル』ぐらいのものではなかろうか。『オリバー・ツイスト』や『二都物語』も映画化、舞台化されており、どこかでご覧になった方も多いだろうが、『大いなる遺産』辺りになると、そろそろ忘れられているかもしれない。日本で言えば幕末から明治初期に生き、多くの作品を残した英国の文豪の、最期の作品がこの『エドウィン・ドルードの謎』だ。ディケンズの他の作品にはないミステリーで、「世界初の推理小説」とも言われている。しかし、この作品を執筆中にディケンズは急死し、「未完」に終わっているのだ。ディケンズの頭の中には、結末や犯人が明確になってはいたのだろうが、少なくもその結末は明らかにされてはいない。つまり、この作品は「途中で終わった推理小説」ということになる。 続きを読む
劇団民藝が、客演に岡本健一を迎え、テネシー・ウィリアムズの『二人だけの芝居』を上演している。舞台芸術が、幕が降りた途端に雲散霧消することに大きな価値の一つがあるのは承知だが、この舞台は後に「平成の演劇史」を語る折に、大きな記念碑となるであろう。第一の理由は、一昨年の2014年に『蝋燭の灯、太陽の光』でウィリアムズの作品の日本初演を果たした民藝が、もう一篇、ウィリアムズの作品を日本で初演した、ということだ。この『二人だけの芝居』は、いまだに人気の衰えないテネシー・ウィリアムズの代表作『ガラスの動物園』や『欲望という名の電車』とは明らかに異質の劇構成や感情によって描かれた作品である。 続きを読む
劇団「ワンツーワークス」が、主宰の古城十忍の作・演出により2011年以来の初演以来、東京で5年ぶりで『死に顔ピース』再演している。一口に言えば、昨今問題になっている「終末医療」をテーマにしたものだ。この芝居の観るべき点は、終末医療を施す医師の側と、末期がんの状況に置かれた家族との両方を対等に描いた部分にある。我々の多くは「患者」の立場に立たされる可能性はあるが、その命を預ける「医師」あるいは関係者の立場に立つことは極めて少ないだろう。 続きを読む
1984年に53歳で亡くなった有吉佐和子の小説を劇化したこの作品、一体何度にわたって劇化、あるいは映像化されたことだろうか。1961年に発表された小説が1973年に小幡欣治により脚色され、初演は芸術座(現・シアタークリエ)だった。以来、キャストを変えながら東宝、新派などで上演されているが、文化座での初演は1977年のことだ。 続きを読む
去年の9月30日に東京・立川で幕を開けた平幹二朗の『王女メディア』が、近畿・中国・四国・中部・北陸・東北・北海道の旅を経て、96ステージ目でこの水戸芸術館で千秋楽を迎えた。1月の上旬に東京グローブ座でも一週間ほどの公演を持ったが、2013年の「一世一代」が好評を受け、82歳にして「一世一代、ふたたび」と銘打って全国を巡演しているのは驚異的なことだ。 続きを読む
男性ばかりの劇団「Studio Life」の創立30周年記念公演の第5弾である。萩尾望都の『トーマの心臓』、『訪問者』、それに朗読劇『湖畔にて』の3作の連鎖公演と銘打ち、2月24日からそれぞれの作品を上演している。「訪問者」は『トーマの心臓』の前段と言うべき作品で、オスカーという少年がドイツの全寮制の学校へ入るまでの、少年時代の物語だ。そこで描かれるのは、オスカーの出生の秘密であり、両親の過去、母親の死の真相である。タイトルの「訪問者」とは、一体誰を指すのだろうか。父親のグスタフにおける子供のオスカーか、グスタフの旧友で、今は高校の校長になったルドルフに対するオスカーなのか。どう解釈するかは観てのお楽しみ、だろう。 続きを読む
一幕の終わり、大きな見せ場でもある「階段落ち」に至るまでの立ち回りで、堂本光一のマイクから苦しそうな息切れが聞こえた。身体も上下に大きく波打っている。スピード感のある動きをあれだけ続けていれば当然だろう。その後、よろめく身体を刀で支えるようにしながら⒛数段の大階段を登り、そこから転がり落ちる。「身体を張った」とか「命懸けの」という言葉がもはや陳腐にも思え、彼はここまで自分を追い詰めて大丈夫なのだろうか、とさえ思う。これが今年で17年目を迎えた「Endless SHOCK 2016」の感想だ。 続きを読む
© 2026 演劇批評
Theme by Anders Noren — ページのトップへ ↑