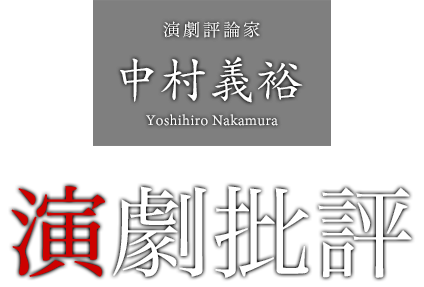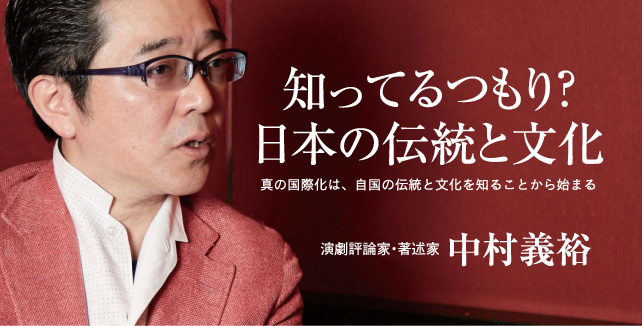まもなく、72回目の終戦記念日を迎える。私のように戦争を知らない世代でも、まだ戦争体験者の声を聴くことが辛うじてできる。しかし、後20年後に、それが可能かどうか。生の声、ではなくとも、戦争の悲惨な体験や経験を作品にしたものは多数あり、それに触れることで、自分なりに戦争について考えることは100年先、200年先でも可能だ。 続きを読む
演劇批評
一覧 (8ページ目/全18ページ)
「大阪松竹座新築開場二十周年記念」「関西・歌舞伎を愛する回 第二十六回」の「角書き(つのがき)」が付いての、夏の大阪での歌舞伎だ。松竹座が開場してもう20年かと思うと、時の流れの速さに驚くと同時に、上方での歌舞伎公演がこうして続いていることにいささかの安心も覚える。もちろん、根付かせた上でさらに発展させるための、並々ならぬ努力と観客の支えがあってのことだ。どんなに良い芝居を上演しても、観客が劇場へ足を運んでくれなければ興行が成立しないのはどの芝居も同じ事だ。 続きを読む
今までにいろいろな組み合わせの舞台を観て来てはいるが、能楽堂で落語を聴いたのは初めてではないだろうか。今年の春に銀座・松坂屋の跡地にオープンした商業施設「GINZA SIX」の地下三階にある「二十五世観世左近記念 観世能楽堂」で、立川志の輔が語る「志の輔らくご」だ。この能楽堂は長らく渋谷・松濤にあったものを、解体し、手入れをして移築したものだ。能楽堂も劇場の一種には違いないが、完全に用途は限られており、その特殊な形状の場所での落語会、相変わらず志の輔のチャレンジ精神は旺盛だ。現在建て替え中の渋谷・パルコ劇場で毎年お正月にたった一人で三席ずつ話していた「志の輔らくご」が、場所を移して銀座で三日間だけの公演に替わったとも言える。 続きを読む
年間十二か月の歌舞伎公演が当たり前になり、他の劇場でも歌舞伎公演を行うのが常態となっている今、毎月の公演が大当たりを望むのは難しい。観客としてはそれを期待したいが、そうも行かないのが現状だ。それにしても、今月の夜の部は、演目の選定や並べ方に「異議あり」というところだ。大幹部クラスは松本幸四郎、中村吉右衛門、片岡仁左衛門の三人。この三人が中心になる演目が据えられるのは当然の成り行きだが、夜の部は吉右衛門の出演はなく、昼の部は仁左衛門が出ていない。夜に幸四郎が二本の演目に出演しており、さらには夜の部は舞踊のような軽い息抜きの幕がない、というのも問題だ。オリンピックを前に、外国人の観客など新たな観客を開拓するためには、開演時間や上演時間の長さもさることながら、今までのような演目の並べ方を根本的に考えることも、歌舞伎に課せられた課題の一つだろう。 続きを読む
五月の大阪・松竹座は、市川猿之助、中村勘九郎、中村七之助の三人を中心とした一座だ。昼の部を猿之助が主役の演目、夜の部は勘九郎・七之助兄弟が主役の演目とし、それぞれが付き合い、得意分野で松竹座の観客を沸かせている。宙乗り、早替わり、本水での立ち回りと各自工夫を凝らした演目に、観客は大喜びだ。 続きを読む
昭和30年代後半に生まれた私にとって、この作品との最初の出会いは映画のスクリーンだった。タイトルも『華麗なるギャツビー』、主演はロバート・レッドフォード、ミア・ファーローという美男美女の代表選手で、1974年の公開である。リアルタイムでは観ておらず、その後、「名画座」の二本立て、三本立てなどで観たのだろう。圧倒的に豪華で華々しく美しい世界に、「これがアメリカか」と単純な憧れを持った記憶がある。 続きを読む
四月の歌舞伎座は、珍しい演目で幕を開けた。中内蝶二という、明治の後半から昭和の初期にかけて活躍した劇作家の作品で『醍醐の花見』。中内蝶二と言えば、劇団新派の初代水谷八重子が井上正夫と演じた『大尉の娘』が有名で、歌舞伎舞踊を書いていたとは知らなかった。もっとも、調べてみると、これは元来が長唄の曲として大正10年に創られたもので、舞踊劇としては今回が初演となる。題名からもわかるように、豊臣秀吉が催した盛大な「醍醐の花見」を舞踊にしたもので、中村鴈治郎の秀吉、中村扇雀の淀の方を中心に、中村壱太郎、尾上松也、中村歌昇などの若手が顔を見せる。
鴈治郎の秀吉が持ち前の愛嬌で秀吉には合った柄で、華やかな花見の様子が描かれるが、幕切れ近くになると松也が演じる甥・秀次の亡霊が現われ、一転、空気が変わる。この辺りの劇的構成が「大正」という時代のモダンな感覚を表現している。若手の顔ぶれを見せるにはよい演目になるかもしれない。
次が、上方の世話物『伊勢音頭恋寝刃』。初役で市川染五郎が福岡貢に挑戦をしている。江戸時代の観客にとっては、生涯に一度は出かけたいと思っていた「伊勢」の風景を見せながら、実際に起きた殺人事件を絡めて創った芝居で、ニュースと観光ガイドをも兼ねていたところにも、江戸時代の歌舞伎の面白さがあったのだろう。
伊勢神宮の御師(神職)・福岡貢を中心に、蜂須賀家の重宝「青江下坂」の名刀を巡って起きる事件に、色恋がからむ芝居だ。「油屋」「奥庭」の場面は上演される機会も多いが、今回は「追駆け」「地蔵堂」「二見ヶ浦」「油屋」「奥庭」と、ほぼ完全な通し上演に近い形での上演である。
染五郎が演じる貢は歌舞伎の役柄では「ぴんとこな」と呼ばれ、柔らかさと強さを合わせ持った上方の二枚目、という役どころだ。今は、上方の演目を上方の役者だけで上演するのはほとんど不可能な状況になってしまった。今回は、貢を持ち役にしている片岡仁左衛門が、染五郎にこの役を教えたという。こうして家を超えて役柄が血縁だけではなく伝承されていくところに、歌舞伎が古典芸能たる値打ちがあるのだろう。
染五郎の貢、全力投球で丁寧に演じている。共演者の尾上松也、中村隼人、中村梅枝、中村米吉らを引っ張りながらの奮闘だ。貢に従う隼人の奴・林平は若くて勢いがあるのがよいが、時に科白の語尾が消えてしまう。こういうところはきっちりやるべきだろう。貢の家来筋で、今は料理人をしている喜助に松也。よい役だが、その良さをまだ見せ切れていない。隼人も松也も、若手が大きな役を自分の物にする機会だ。物怖じせずにぶつかってほしい。貢の主筋に当たる若旦那・今田万次郎に片岡秀太郎。今回のメンバーの中では最年長だが、上方の色気を持つ貴重な役者で、「つっころばし」と呼ばれる、突けば倒れるような若旦那の風情がある。これが芸の年輪でもあろう。
貢の恋人で、梅枝が演じるお紺が愛想尽かしをするのが後半の悲劇になる。若さは買えるが、まだまだ勉強の段階。二人の恋路を邪魔する仲居・万野に市川猿之助。意地が悪い役で、あえて女形の声を造らずに地声で演じているのが良い。ただ、もっと意地悪く、粘着質に演じてもよいだろう。そうしないと、染五郎の貢を精神的に追い詰め、刀で叩かせるという偶発的な事故にまで至らない。こうした過程を経て、忠義を尽くそうとした貢が、回りの思惑や食い違いで人を殺めてしまう悲劇が、だんだん引き立ってゆくのだ。それを土地の名物や風俗を織り交ぜながら見せるこうした芝居は、次の時代へ残したい物の一つだ。
昼の部の最後が松本幸四郎の『熊谷陣屋』。幸四郎を襲名して13回目の上演だという。妻の相模が猿之助、藤の方が市川高麗蔵、弥陀六が左團次、義経に染五郎という配役。幸四郎は「若い頃は主君への忠義として我が子を殺す、という演じ方をしていたが、最近は戦場に咲いた儚い夫婦愛を描きたい」とプログラムで語っている。そのゆえかどうか、今回の猿之助、高麗蔵の配役が、この一幕で今までとは違う風景を見せた。
今までの『熊谷陣屋』では、相模を一座の立女形、藤の方をその次位の役者という配役での上演が多く、それを見慣れていたが、今回は藤の方の高麗蔵の方が、立女形ではないにしても年齢も上のベテランで貫禄もある。本来、藤の方は、勇壮な武士の熊谷直実が頭を下げる立場の女性だ。それが、熊谷の妻・相模に若い猿之助を配することで、両者の関係性がごく自然に見える。古い観客には半ば常識になっていることを、改めて考え直した結果だろうが、この組み合わせがうまく行った。猿之助も内輪に抑えた芝居で、『伊勢音頭』の万野で見せた味とは違った顔を見せた。
染五郎の義経、襖が開いた瞬間からいかにも源氏の御大将という品格を見せる。口跡もよく、いい義経だ。義経が桜に託した謎を読み解き、平家の若き公達・敦盛を助ける代わりに我が子の首を差し出す熊谷直実。昭和56年に幸四郎が現在の名前を襲名した折の舞台以来、十七世中村勘三郎、中村吉右衛門、二世尾上松緑、十二世市川團十郎、片岡仁左衛門、十世坂東三津五郎、市川染五郎、中村芝翫などの熊谷を観て来たが、やはりこの役は幸四郎のものだろう。
武士として避けることのできない悲劇を内包しながら、妻と共に我が子を切らねばならなかった哀しみを胸に抱く「一人の男」として、渾身の演技を見せ、昼の部では一番の出来だ。相模との会話も、常に上からの強い調子で叩きつけるようなものだけではないところにそうした工夫が感じられる。
特に、幕切れの「十六年は一昔」の科白で有名な花道の引っ込みで、今まで武士としての本分のために、堪えに堪えて来た哀しみが一気に噴き出す。自分の役目は果たした、と義経の許しをもらって僧形となる。そこへ戦場の騒ぎが聞こえ一瞬武士の感覚に戻るが、それを振り払い、花道を引っ込む。その時に、「アッ」と言い、持っている笠を杖で叩く。今までに観たことのない物で、昨年10月に国立劇場で『仮名手本忠臣蔵』の「四段目」で大星由良助を演じた時にも同じような演技を見た。これは、役柄を踏まえた上での一人の人間の「叫び」だ。
この一言があることで、立派な武将も一人の人間、子を持つ父であることが鮮明になる。来年の襲名を控え、新しい方法を模索している姿が、幕切れの僧形と重なり、求道者のようにも見える。櫻の見ごろは終わったが、義経が大切にしている舞台の櫻が、多くを語っているように思える。充実した昼の部になった。
「エッグ・スタンド」2017.03.02 シアター・サンモール
男優だけでどんな芝居も演じてしまう「スタジオライフ」。1985年に結成以来、30年を超える歴史を持ち、昨今賑やかな「イケメン・ブーム」の到来よりもはるかに歴史は古い。萩尾望都の『トーマの心臓』、『訪問者』や、皆川博子の『死の泉』、手塚治虫の『アドルフに告ぐ』などの作品を、劇団の座付き作家であり、唯一の女性である倉田淳が脚色し、多くの佳作を残して来た。この『エッグ・スタンド』も萩尾望都の作品だ。
「スタジオライフ」の公演の特徴は、主要なキャストをダブルで演じることだ。倉田によれば、頭の中で配役を考えていると、主な役は一人に決め兼ねる場合が多いのだ、と聞いたことがある。観客にすれば、二通りの組み合わせで観られるわけだが、最近はこうした仕組みの公演が多い。とは言え、他の劇場のダブル・キャストの仕組みとは根っこが違っているのがわかる。この劇団のキャスティングが特殊なのは、ダブル・キャストの場合は、二役を演じることだろう。今回の芝居の役名で言えば、「ルイーズ」と「サガン未亡人」がセットになっており、互いがどちらかを演じている、という仕組みだ。これが、他芝居のダブル、トリプルキャストとの公演の違いだ。
さて、「エッグ・スタンド」である。第二次世界大戦の最中、ドイツ軍に占領されたパリ。キャバレーの踊り子・ルイーズと素性がよくわからない少年・ラウル、地下に潜行してレジスタンスの活動をしているマルシャンの三人が主人公となる。接点のなかった三人が共同生活を進めるうちに、ルイーズがユダヤ人の血を引いていることがわかる…。
もはや、戦後も70年を過ぎ、戦時中のことはおろか戦後の大きな時代の動きも忘れ去られようとしている。その中で、この作品は、「戦争反対」を声高に叫ぶわけではない。偶然なのか必然なのか、出会って共同生活を始めた三人のギリギリの瀬戸際に立たされた生活を「点景」のように描く。そして、物語は重い結末へと向かう。その中で、彼らだけではなく、多くの人々が本意ではない苦渋の生活を送らねばならない時代、その背景にあったものの闇の深さが浮き彫りにされ、炙り出されてくる芝居だ。
倉田脚色は、台本が長い傾向がある。しかし、この芝居は90分を僅かに超える一幕物で、異例とも言える短さだ。それは、会話の行間に込められている想いが深いこと、また、タイトルの「エッグ・スタンド」という言葉が示すように、何らかの比喩として託された言葉が多いことによる。それらに多くのメッセージや深い感情の動きがあるために、これを2時間あるいは2時間半という長さにすると、観客が、作品が発する大切なメッセージを受け取れ切れない可能性があるのだ。
たとえ短くとも、萩尾望都の原作、倉田淳の脚色・演出が優れており、無駄な会話が必要ではない、ということもある。私は勉強不足なことに原作を読んでいないので、どこがどのように違う、という比較はできない。ただ、殊更に騒ぎ立てることなく、さりげない会話の積み重ねで、内在する問題の重さや時代の暗さ、生きる厳しさを描くのは容易なことではない。そんな作品に果敢に挑戦した姿勢は評価したいと思う。
Rougeチームの初日に当たる今日は、山本芳樹のラウル、久保優二のルイーズ、笠原浩夫のマルシャンのトリオだった。初日ゆえか、芝居にまだ硬さが見られ、こなれていない部分が散見された。今までに劇団が手掛けて来た作品との性質の違いによる戸惑いもあっただろう。もう一つのNoirチームは未見のため比較はできないが、Rougeチームでもまだ作品が身体の中に落とし込めていない俳優が何名かいたのは事実だ。台詞の裏側にあるメッセージやその想いを肉体で表現することの難しさに苦しむ若い俳優も多いだろう。しかし、こうした挑戦を重ねることで、新しい世代も育つ。その過程であり、新しい作品、新しい道の開拓は厳しいものだ。しかし、ここを超えないと新しい芽は吹かない。そのために頑張ってほしいところだ。
2000年に『MILLENNIUM SHOCK』の名で幕を開けた作品が途中で名前を変え、今回の公演の千秋楽で上演回数が1500回に達するという。17年前に、当時、帝国劇場で「最年少座長」という記録を作って以来の時間を考えれば、かなりのスピードである。しかし、主演の堂本光一にとっては、上演回数は重要な問題ではなく、単なる「通過点」に過ぎないのだろう。この作品に一貫しているテーマである「Show must go on」の言葉通りに、まだまだこの舞台は続くはずだ。 続きを読む
大阪・松竹座のお正月、昼の部は『吉例寿曽我』で幕を開ける。お正月に「曽我物」というのは江戸以来の伝統で、最もよく知られているのは『寿曽我対面』だが、この芝居は座頭が勤めるのが慣例の工藤祐経をその妻が女形で演じる、という珍しい作品だ。70数年ぶりの上演ということで、工藤祐経の妻・梛の葉御前(なぎのはごぜん)を片岡秀太郎、曽我五郎・十郎をそれぞれ幼名の箱王、一万で中村福之助の箱王、中村歌之助の一万、中村橋之助が小林朝比奈で三兄弟が顔を合わせる。 続きを読む
© 2026 演劇批評
Theme by Anders Noren — ページのトップへ ↑