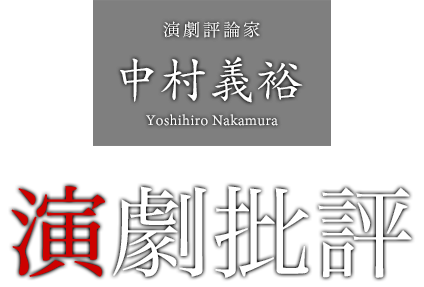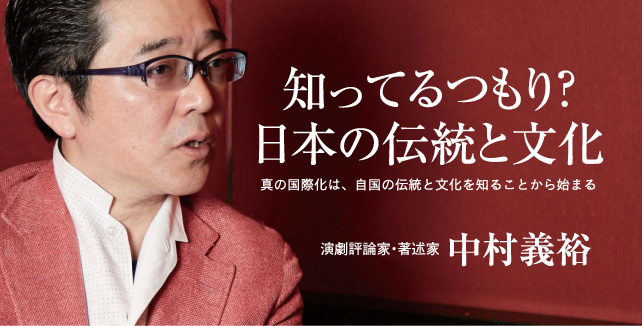一月に歌舞伎座で幕を開けた「高麗屋三代襲名披露公演」が四月の名古屋・御園座を経て、博多座で幕を開けた。今月は、新・市川染五郎は学業のため、舞台での披露は九代目松本幸四郎改め二代目松本白鸚、七代目市川染五郎改め十代目松本幸四郎の親子を中心に、坂田藤十郎、片岡仁左衛門、中村梅玉、中村魁春、中村鴈治郎、市川高麗蔵、大谷友右衛門らの顔ぶれだ。 続きを読む
演劇批評
一覧 (6ページ目/全18ページ)
今の我々は、必ず訪れる「死」を必死で見ないように、あるいは触れないようにと、全力を以て遠ざけている。いつの間にか人生は100年の時代になり、「健康のためなら死ねる」というジョークがその意味をなさなくなってしまった。健康で長生きをしなければ損をしたかのような風潮で、きちんと死に対面もしようとしなければ、日常的に死を想うこともない。哲学者「メメント・モリ」(死を想え)という深遠な言葉など糞くらえ、と言わんばかりだ。 続きを読む
老朽化のため閉場し、新築再開場が待たれていた名古屋・御園座のこけら落とし公演は、一、二月に歌舞伎座で始まった「高麗屋三代襲名」を以て幕を開けた。厳密には、新・市川染五郎は学業のため今月は出演しないが、親・子・孫の三代が新しい名前を襲名することに変わりはない。九代目松本幸四郎改め二代目松本白鸚、七代目市川染五郎改め十代目松本幸四郎の親子が中心となって、昼の部三本、夜の部三本、当たり役あり初役での挑戦ありと、バラエティに富んだ演目が並んでいる。 続きを読む
1969年の開場以来、劇団青年座の拠点となっていた東京・代々木八幡の青年座劇場が、ビルの老朽化のために建て替えとなり、今回の第231回公演『砂塵のニケ』を以て一時休館となる。半世紀に近い歴史の中で幾多の名作・名優を生み出した功績は、日本の新劇史の一角にきちんと留めておくべきだろう。脚本は、若手の劇作家として活躍著しい長田育恵、演出は宮田慶子。プログラムにもあるが、最近は中津留章仁、野木萌葱、前川知大、蓬莱竜太、そして今回の長田育恵など、1970年代生まれの作家との取り組みが目立つ。これは青年座に限ったことではなく、演劇界の潮流が変わり始めた「潮目」の一つでもあろう。 続きを読む
今回の帝国劇場公演で、上演回数が通算1,600回を迎えるという。ファンにとっても、主演の堂本光一にとっても、この舞台のために日々を重ねている部分は大きいだろう。もちろんそれだけではないだろうが、多くの仕事を抱える中で、「この時期が来た」とおいそれとできるものではない。入念な準備を重ねた上のことで、千秋楽が終わった瞬間に翌年のことを考え始めるぐらいでなければ、この過酷な舞台を演じ続けることは叶わないだろう。 続きを読む
高麗屋三代襲名披露興行も二か月目に入った。一月の公演を経て、襲名する三人が、もう新しい名前に馴染んでいる感覚がある。襲名の不思議なところだ。 続きを読む
高麗屋三代襲名披露公演、昼の部は『箱根霊験誓仇討』(はこねれいげんちかいのあだうち)で幕を開ける。タイトルからもわかるように仇討ち物だが、滅多に上演されない。前回の上演が平成16年12月の京都・南座の顔見世興行、その前は昭和53年10月の歌舞伎座で、十七世中村勘三郎の勝五郎、六世中村歌右衛門の初花、八代目松本幸四郎(当時、のちに初代松本白鸚)の滝口上野(たきぐち・こうづけ)と奴・筆助の二役という配役で、私が観た舞台もこれだった。東京では、実に40年ぶりの上演となる。ただし、前回の上演からタイトルが変わっており、本来は『箱根霊験躄仇討』(はこねれいげんいざりのあだうち)で、昭和期の舞台もそうであった。 続きを読む
今年のお正月の歌舞伎座は、37年ぶりの「高麗屋三代襲名」で幕を開ける。九代目松本幸四郎が二代目松本白鸚に、七代目市川染五郎が十代目松本幸四郎に、松本金太郎が八代目市川染五郎にと、それぞれが父の名を襲名する興行だ。どの襲名もおめでたいものだが、「三代」同時は稀で、親・子・孫、それぞれの世代が次の名を襲名するに相応しい活躍をしている、と衆目が一致しなければできることではない。それを二回できるのは、現・白鸚の言葉を借りればまさに「奇蹟」だ。前回の三代襲名は、10月、11月の歌舞伎座で行われた。私はまだ高校生だったが、三階席で観た二ヶ月の舞台はくっきりと焼き付いている。それから37年が過ぎたと思うと、あっという間だと感じると同時に、役者と観客が共に年月を重ねる芸能である歌舞伎の喜びと本質をも感じる。 続きを読む
初演から65年を経てもなお、多くの劇団やカンパニーで手掛けている名作である。アーサー・ミラーの『セールスマンの死』と並んで、現代アメリカ演劇の金字塔と称されることも多く、過去の舞台で言えば杉村春子、東恵美子、二代目水谷八重子(上演当時は水谷良重)、栗原小巻、樋口可南子、男優ではあるが「女形」の篠井英介、そして大竹しのぶと7人の「ブランチ」の姿を観て来たことになる。今回の舞台は、2002年に蜷川幸雄が演出したものの再演で、今回は演出にフィリップ・ブリーンが当たっている。 続きを読む
タイトルがすべてひらがなで、一瞬、上から読んでも下から読んでも同じ「回文」ではないか、と錯覚するような珍しい名前だ。2015年に長塚圭史の作・演出で上演されたものの再演で、登場人物は長塚を含め4人。「たなか」に首藤康之、「かなた」に近藤良平、「けいこ」に松たか子、「こいけ」に長塚圭史という配役だ。 続きを読む
© 2026 演劇批評
Theme by Anders Noren — ページのトップへ ↑