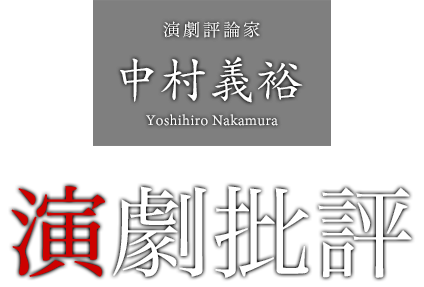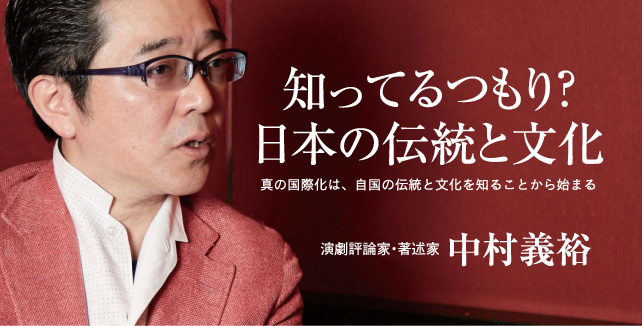著名な作家が若い頃の習作時代などに書いた作品を「若書き」と呼ぶ。場合によっては玉石混交だったりするケースがあるが、アメリカ現代演劇を象徴する劇作家の一人であるテネシー・ウィリアムズが、1937年、26歳の折にこれほど骨格の太い芝居を書いていたというのは驚きだ。しかも、発表当時にアマチュア劇団で上演されただけで、活字になったのが2004年、作者が亡くなって21年後のことであり、日本では今回の舞台が初演となる。アメリカ・アラバマ州の炭鉱の町で貧困に喘ぐ人々の姿を10年間の間に三世代の人物を主軸に描いたこの作品は、非常にがっしりとした骨格を持ち、若書きでありながら破綻なく緻密に計算されている。翻訳者の吉原豊司によれば、この作品にはジョセフ・フェーラン・ホリフィールドという共作者がおり、この人が書いた一幕劇を、ウィリアムズが二幕十場という構成に膨らませたもののようだ。
続きを読む
演劇批評
一覧 (18ページ目/全18ページ)

「左より 日色ともゑ、岩谷優志 写真提供:劇団民藝」
2005年にこのタイトルでの上演が始まって以来、今年で10年とは早いものだ。ファンにとっては、「年に一度のお楽しみ」となった恒例の舞台だろう。昨年の3月21日には2000年の『SHOCK』初演以来、1000回の上演を迎えた。毎年、マイナーチェンジを繰り返しながら、エンタテインメントとしての「進化」を続けていることになる。同じ演目で単独主演が1000回を越えているのは森光子の『放浪記』、松本幸四郎の『ラ・マンチャの男』、『勧進帳』、山本安英の『夕鶴』しかない。いずれも長い年月を掛けて積み重ねて来たもので、堂本光一の場合はわずか14年でこの偉業を達したことになる。もっとも、回数を重ねることは大事なことだが、演じる方も観客も「その日一回」の舞台であり、そこにいかに精魂を込められるか、だろう。
続きを読む
今月の明治座は、通常の「座長公演」ではなく、「ダブル座長」だ。松平健が主演する「暴れん坊将軍」と「唄う絵草紙」の公演に川中美幸がゲストで出演、川中美幸が座長で演じる「赤穂の寒桜」と「人・うた・心」に松平健がゲストで出演するという贅沢なもの。例を挙げれば、昼の部は松平健の座長公演で川中美幸がゲスト出演、夜の部はその逆、ということだ。一ヶ月の公演の中で、二回の座長公演を観ることができるのは面白い。いろいろな意味で停滞し、暗いニュースが多い演劇界で斬新な試みだが、実は今回が初めてではない。昨年の三月をもって改築のため閉館した名古屋・御園座の「さよなら公演」で、ちょうど一年前に実現した顔合わせの東京公演である。
続きを読む
日本一チケットの取りにくい落語家と言われている立川志の輔のパルコ劇場一ヶ月公演も今年で九年目を迎えるという。一人で毎回三席、オリジナル、新作、古典と、休演日はあるにせよ一ヶ月続けるというのは尋常な話ではない。本人いわく、「武道館でやっちゃえば一回で終わるんだけど、落語ってそういう性質のものじゃないから」。まさにその通りだが、一ヶ月を噺し続けるのは並大抵の技ではない。しかし、気力・体力・技術がそれを可能にし、何よりも多くの人がこの公演を待っている。先年亡くなった志の輔の師匠・立川談志は天才とも異才とも言われ、名人の名をほしいままにした。さすがにその弟子だけのことはあるが、談志の芸が客を選ぶ性質があったのに比べ、志の輔の芸は良い意味で万人向けである。古典落語でも、「いかに現代のお客様に分かりやすいものにするか」に心を砕いているのがハッキリと分かる。また、オリジナルや新作でも、まさに「現代の落語」のあり方や本質を探りながら、自ら創り、練り上げている。師匠・談志の功績が平成に名人芸を遺したことであるとするなら、志の輔の功績は、落語の寿命を少なくも20年から30年は延ばしたことだろう。その証拠に、今の落語界に元気があるとは言え、男女を問わず若い観客の姿がずいぶん増えた。
続きを読む
多くの若者が、突拍子もないとは言いながらいろいろな夢を見ていた時代が、ついこの間までの日本にはあったような気がする。私の視界に入る若者たちがいささか元気をなくしているだけなのかも知れないが、今回、アミューズ・ミュージカルシアターで上演されている韓国ミュージカル「RUN TO YOU」には、ナイトクラブで働きながら音楽の世界でスターになりたい3人の若者の夢が語られている。かつての無謀で何も知らなかった頃の自分の姿を見るような想いでもある。ナイトクラブで働き、無断で寝泊りして練習を繰り返していた3人組が、社長にたたき出されるが、退職金代わりにもらったオーディションのチャンスで見事にデビューを果たす。しかし、「スターになる以上、恋愛は禁止」と、ジェミニと恋人の仲はだんだんに離れてゆく…。
続きを読む
© 2026 演劇批評
Theme by Anders Noren — ページのトップへ ↑