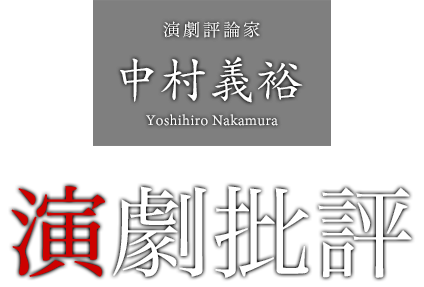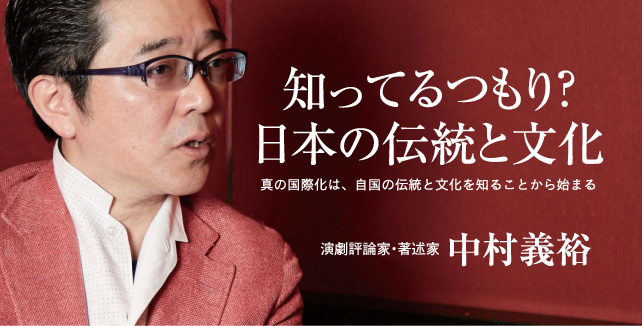「夢一夜」 2017.12.07 紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA
加藤健一事務所の100回目の公演は『夢一夜』というフランス系アメリカ人の劇作家、カトリーヌ・フィユーの作品である。現在は、「性的マイノリティ」については「LGBT」という言葉も一般的になり、理解が進み始めているが、そうした人々と、アメリカの「アーミッシュ」と呼ばれるキリスト教の純粋さを維持しながら生活する保守派の人々が主人公になった、面白い芝居を取り上げた。「アーミッシュ」とは耳慣れない言葉で、キリスト教徒がアメリカへ移民した当時の生活様式を基本とし、近代以前の伝統的な技術しか使わずに生活を送る人びとだ。電気を使わず、電話も家庭内には置かずに、集団の中で緊急時のために共用で置き、移動も自動車ではなく馬車を主としている。服装も生活も極めて質素で、現代の利便と欲望からは遠ざかった場所での生活を旨としている。 続きを読む
顔見世興行・夜の部は、『仮名手本忠臣蔵』から『五段目』と『六段目』、上方狂言の『新口村』(にのくちむら)、真山青果の『元禄忠臣蔵』より『大石最後の一日』と、ボリュームのある献立が並んだ。特に、最後の『大石最後の一日』は、来年1月、2月と親子孫の三代で襲名披露を行う松本幸四郎一家が現在の名で揃って踏む最後の舞台でもある。昼の部の批評でも書いたことだが、「大幹部」クラスはそれぞれの当たり役に一世一代の覚悟で臨んでいるような充実感と、その先を想う一抹の寂しさに溢れる。 続きを読む
来年一月・二月の歌舞伎座での親子三代襲名披露公演を控え、松本幸四郎、市川染五郎、松本金太郎の三代が揃って現在の名前で舞台を踏む最後の公演となった。十一月の顔見世だけあって昼夜共にベテラン・若手と豪華な顔ぶれが並んでいる。その一方で、ベテラン勢にとっては今回が「一世一代」の気持ちで演じている物も多いだろう。歌舞伎界の世代交替を確実に感じさせる公演でもある。 続きを読む
現代の演劇から薄れたものの一つが「土俗的なにおい」、平たく言えば「土臭さ」だろう。俳優をはじめ、舞台装置、効果、演出など、芝居を構成する要素がどんどん洗練されてゆく中で、昔ながらの「土臭さ」を持った一人芝居を、コツコツと全国各地で上演している坂本長利の『土佐源氏』。その初演は1967年、今からちょうど50年前のことになる。 続きを読む
考えてみると、最近、ブレヒト(1898~1956)の舞台を目にする機会が一時に比べて減ったような感覚がある。20世紀の演劇史に大きな名前を刻んだ偉大なドイツの劇作家、ブレヒトの代表作の一つ、『肝っ玉おっ母と子供たち』に、84歳になる仲代達矢が無名塾の面々を率いて、能登演劇堂で29年ぶりに上演している。 続きを読む
初演以来35年、このステージが450回目となった松本幸四郎の『アマデウス』。今回と同じサンシャイン劇場での初演の舞台を懐かしく想い出すと同時に、もうそんな歳月が流れたのか、とも思う。映画化もされたこの作品は、天才として知られるアマデウス・モーツァルトと、その才能に嫉妬する宮廷音楽家・サリエーリとの確執を描いたドラマとして、今回が九回目の上演となる。サリエーリは一貫して幸四郎が演じ続け、モーツァルトは江守徹の初演を経て、その後、幸四郎の子息・市川染五郎、武田真治、今回は桐山照史。モーツァルトの妻・コンスタンツェは大和田美帆。 続きを読む
最近のテレビドラマでは珍しく大きな話題を呼び、つい先日最終回の放送を終えた「やすらぎの郷」。かつて、テレビ界に貢献した人が集まって暮らす無料老人ホームで起きるドラマの数々と、往年の豪華スターたちのキャスティングが注目を集めた。この作品、『想い出のカルテット』は、引退した音楽家たちが暮らす老人ホームが舞台で、2011年にルテアトル銀座で初演、14年に今回と同じEXシアター六本木のオープニング・シリーズとして再演され、今回が三回目の上演となる。黒柳徹子が1989年に当時の銀座セゾン劇場で始めた海外コメディ・シリーズの一作で、今回が第31弾となる。 続きを読む
数年前から、演劇の世界で「2,5次元」という言葉が使われるようになった。主にミュージカルだが、必ずしもそればかりではない。私の解釈では、マンガやアニメーションなど「二次元」の作品をもとに舞台化したものを「2,5次元」と呼んでいるようだ。元を正せば小説も戯曲も紙に印刷された「二次元」の世界の産物で、意味は同じでも、あえて素材をマンガなどに求め、新たな工夫を加えて舞台化する、というところに「2,5次元」の工夫があるのだろう。 続きを読む
八月の歌舞伎座で恒例となった三部制の公演、今年も若手が大いに汗を流している。古典、新歌舞伎、新作など、バラエティに富んだ演目が並んでおり、若手・花形と呼ばれる世代の役者たちのエネルギーの発露を感じる。第三部は、野田秀樹が坂口安吾の『桜の森の満開の下』などの作品をもとに、自らの世界観で劇化した『野田版・桜の森の満開の下』。1992年の初演時は『贋作・桜の森の満開の下』となっていたが、脚本の内容も変わり、今回の「野田版」が決定版とも言えよう。亡き中村勘三郎の盟友でもあった野田秀樹の作品を、遺児の中村勘九郎・七之助の兄弟を中心に演じることに、勘三郎へのオマージュが感じられる。 続きを読む
多くの和太鼓集団が、それぞれの個性を持って活動を繰り広げている。大きなものになると直径が2メートルを超える迫力のある太鼓の音は、客席に座っている観客の身体に直接響くほどの重みを持っている。その響きや音質が、我々日本人が持っている「原初の感覚」を呼び覚ますのだろう。だから、多くの和太鼓集団が支持を集めているのだ。 続きを読む