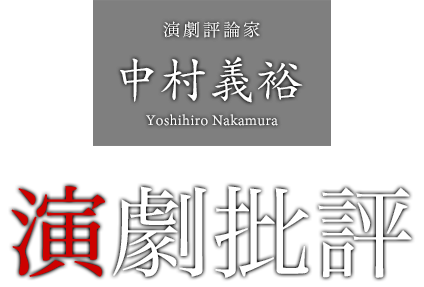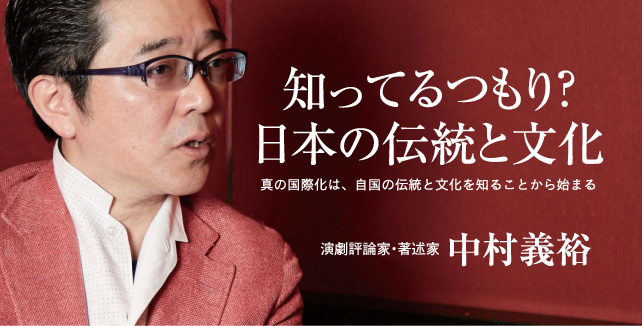幕が開いて2分後には、主な登場人物である兄弟が、猛烈な勢いで喧嘩をしている。その言葉は下品で薄汚く、世間一般の常識に照らし合わせても、わざわざ罵り合いをするほどの問題でもない。しかも、二人はたった今、父の葬儀を終えて家に帰ったばかりなのだ。神父が慌てて仲裁に入るものの、ハエが止まったほどにも感じていない。
ロンドン生まれのアイルランド人であるマーティン・マクドナーの『ロンサム・ウエスト』。兄のコールマン(堤真一)、弟のヴァレン(瑛太)、ウェルシュ神父(北村有起哉)、近所の女の子、ガーリーン(木下あかり)。登場人物はこの四人だけの一幕物の芝居だ。アイルランドの片田舎を舞台に、決して裕福とは思えない兄弟が、きっかけを探しては取っ組み合い、罵り合い、喧嘩ばかりしている。たまに、一陣の風が吹き抜けるように、二人の生活に彩りを与えているのがガーリーンだ。神父は二人のために何を説いても、自分の無力感に、兄弟と一緒になって酒に溺れている始末。この兄弟は何を考えて生きているのだろうか。「いかにして、一瞬でも相手より優位に立つか」だ。こんなバカげた話はあるまい、と芝居を眺めていると、戯曲の持つ力に引き込まれてゆく…。
続きを読む
1986年以来恒例となっている前進座の五月・国立劇場公演は、鶴屋南北の『お染の七役』だ。ちょうど80年前の1934年、まだ劇団が創立して間もない頃に、先代の五世河原崎国太郎が、渥美清太郎の改訂・脚本で復活上演し、七役を演じて歌舞伎界でのスタンダードな演目となったものだ。以降、坂東玉三郎や中村福助、そして当代の六代目国太郎が演じ、女形の人気演目となった。当代は16年前に国太郎を襲名した折の演目でもあり、祖父以来の前進座の財産演目ということからも、今回の上演に当たっての感慨は一入であろう。今月は明治座で同じ鶴屋南北の『伊達の十役』を市川染五郎が演じており、期せずして南北の「早替わり作品」の競演となった。
続きを読む
美輪明宏がこの作品を初演したのは、約35年前の渋谷「ジァン・ジァン」だと言う。以降、博品館劇場、サンシャイン劇場、ルテアトル銀座とだんだん大きな劇場で回数を重ねて来た。私が最初にこの舞台を観たのは、1981年のサンシャイン劇場での舞台で、この時は二回の休憩を含め、上演時間が3時間だった。今回は、同様の形態で上演時間が3時間40分である。作・演出も美輪自らが行う中で、試行錯誤を繰り返し、内容がどんどん膨らんできた結果であろう。それでもなお、前回に観た舞台と比べると、ピアフの友人の部屋の場面がカットされていたりと、その時々に工夫がなされており、タイトルにも「美輪明宏版 愛の讃歌」と銘打ってある。いまだに現在進行形の舞台、というわけだ。
続きを読む
日本が「国立の」オペラハウスを持てたのが歴史的な眼で見ればつい最近のことだが、「国立」に囚われずにどんどん新しい試みを行っているのは評価に値する。今回上演された二本のバレエのうち、「ファスター」は日本初演である。2012年のロンドン五輪の折に、オーストラリアの作曲家・マシュー・ハインドソンがオーケストラのために委嘱された作品に、この公演の芸術監督であるデヴィッド・ビントレーが振付を行ったもので、サブ・タイトルに「オリンピックのモットー『より速く、より高く、より強く』にインスパイアされた、デヴィッド・ビントレーのバレエのための音楽」とある。ここからも分かるように、アスリートたちを主人公にした作品で、40分の小品が「闘う」「投げる」「跳ぶ」「シンクロ」「マラソン」「チームA」「チームB」と分けられており、ダンサーたちが全肉体を駆使し、跳躍し、走る姿は、まるでスポーツのようだ。バレエも究極的には美術も何もいらず、演者の肉体美そのものが芸術品になる、という例だろう。男女を問わず、確かにその肉体美は美しく、中には一瞬、本当のアスリートが混ざっているのではないかと錯覚さえするほどだ。それほどに鍛え上げられた肉体をもってしても、この40分の作品はいかにもハードで、ダンサーの肉体の限界に挑むような側面をも持っている。主な役のいくつかはダブル・キャストで、私が観た舞台では小野絢子と福岡雄大が今後の可能性を感じさせる素材の魅力を感じさせた。
続きを読む
諸田玲子の小説『きりきり舞い』を原作に、田村孝裕の脚本、上村聡史の演出で、田中麗奈の主演で「時代劇コメディ」が上演されている。加藤雅也演じる十返舎一九の娘・舞を田中が演じ、熊谷真実の一九の妻・えつを中心に、板尾創路の葛飾北斎、篠井英介の踊りの師匠・勘弥姐さんなどの「奇人」ばかりが集まる中での騒動を描いた二幕物だ。最近の時代劇では、洋楽が使われることにだんだん観客も違和感がなくなって来た。こういう方法も悪くはないが、今回の場合で言えば科白のアクセントが現代調の役者と、時代劇の役者が混在していた。これは、どちらかの時代でまとめた方がすっきりしただろう。一幕、二幕がそれぞれ80分で十一場、十二場と場面転換が多いが、昨今ありがちなテレビのカットのようなめまぐるしさではなく、見せるべき場面にはきちんと時間を掛けている創り方には好感が持てる。若い感性が大劇場演劇の中で、どういう才能を発揮してくれるか、これは今後の演劇界に大きな期待が寄せられると同時に、試行錯誤を繰り返さなくてはならない問題でもある。
続きを読む
歌舞伎では、作品の構造を現わすために、「世界」という言葉を使う。みんなが良く知る過去の物語や事件を素材にし、これを大きな骨組みとして芝居を組み立ててゆく。この素材になるものが「世界」だ。例えて言えば「平家物語」であり「太平記」だ。そこに、作者ならではのアイディアである「趣向」を加え、今の言葉で言えばいかに「オリジナリティ」を出すか、今までにない面白さを見せるか、が作者の腕だ。
続きを読む
江戸時代の風情を今に残す香川県「金丸座」での「こんぴら歌舞伎」も、今年で三十回目を迎えた。早いものだと感じると同時に、こうした試みが地域の芸能としてしっかり根付いたことの嬉しさをも感じる。今年は市川染五郎を座頭に、中村壱太郎、上村吉弥、尾上松也などの顔ぶれで一座が開いた。ちょうど桜も見ごろで、春の旅にはよいかもしれない。
夜の部、『女殺油地獄』、この頃は油まみれの殺しを見せる「豊嶋屋内」で終わらせずに、その後の場面まで上演するケースが増えて来たが、これは良い傾向だ。河内屋与兵衛という青年のその場限りの行動がどう完結するか、そこまでをキチンと作品として見せることになるからだ。
続きを読む
この芝居の作者・山谷典子は30代後半の女性で、文学座の女優でもある。また、自ら演劇集団「Ring-Bong」を立ち上げ、主宰・劇作・出演を行っている、何ともパワフルな女優だ。そんな女性がタイトルを一見しただけでは内容が想像できない芝居でこだわっているのが「戦争」だ。もちろん、彼女は戦争を知らない世代である。しかし、彼女が祖父母の世代から見聞きしたことは、まだ生々しさを失うことなく残っており、そこへ現代の「戦争」とも言える原子力の問題を絡めた作品だ。私も、作者も当然ながら戦争を知らない世代だ。しかし、「東日本大震災」を機にまだ収束の見通しがつかない原発の問題は、我々の世代にとって、ある意味での戦争ではないか、と私は考えている。そうした感覚を、若い世代の作家が肌で感じ、先の大戦との共通項を見つけて一本の芝居にまとめた、という点では観客として共感できる。
続きを読む
病院でも患者に「様」を付けて呼んだり、プライバシー保護のために入院病棟の部屋には名札を掲げない病院も出て来た。時代の流れとは言え、世の中も変われば変わるものだ。この芝居も、巷によくある「名医100人」のような話題かと思って客席に付いたら、そこへ行く以前の問題を喜劇にしたものだ。コメディ専門のテアトル・エコーの面目躍如とも言える舞台で、病院の格付け「ミシュラン」の調査員が潜入しているとの噂が、大きいとは言えない病院の中でドタバタの騒動を巻き起こす。面白い芝居だが、今の時代、事実だと言われてもおかしくないようなリアリティをも持っている。
続きを読む
20世紀を代表する哲学者・サルトル。日本でも一時はブームのようにサルトルの戯曲を上演していた時代があった。しかし、それからしばらく、サルトルの戯曲はなぜか姿を消していた。私の記憶にあるのは『狂気と天才』ぐらいのものだろうか。「哲学者が書いた芝居」というイメージで難解と取られ、このところ上演頻度が減っていたが、1960年代から70年代にかけては、サルトルの芝居がずいぶんと上演された。特徴的なのは、プロの俳優ではなく、学生演劇での上演がかなりの数を占めていたことだ。学生運動の盛んな時代に、そのエネルギーは表現としての学生演劇にも放たれ、そこで多くの作品が上演されたのだ。この『アルトナの幽閉者』にしても、1961年に俳優小劇場の旗揚げ公演で『アルトナの監禁された人たち』の名で上演され、その後、1967年に早稲田大学の劇研が『アルトナの幽閉者』として上演して以来である。
続きを読む