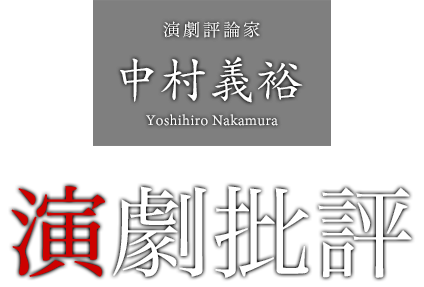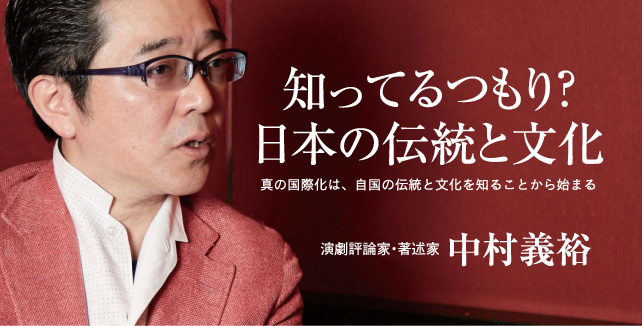二世中村吉右衛門がテレビで人気を博し、28年間にわたって放送された『鬼平犯科帳』。キチンと作られた池波正太郎の原作があってこそだが、今月の歌舞伎座では、松本幸四郎が鬼平を演じている。実は、これは鬼平にとっては「里帰り」を果たしたようなもので、本来、この物語は、幸四郎の祖父・八世松本幸四郎(1910~1982)をモデルに書かれ、昭和44年から翌年にかけて放映されたものだ。その後、次男の吉右衛門、そして今回は八世の孫に当たる当代の幸四郎が演じている。
舞台での初演は放送の翌45年の帝国劇場で、ゲストに山田五十鈴(1917~2012)を迎えた豪華なものだった。この当時、幸四郎一門は現在の二代目松本白鸚、吉右衛門兄弟と共に松竹を離れ、東宝に移籍していた時代で、女優が歌舞伎へ出ることなど問題にはならなかった。吉右衛門が前名の「中村萬之助」から「中村吉右衛門」を襲名したのも、歌舞伎座ではなく、改築新装開場した帝国劇場だった。
歌舞伎の本丸・松竹にしても、昭和20年代には、新派の初代水谷八重子(1905~1979)が初代市川猿翁(1888~1963)の公演などに何度も出演している。歌舞伎に女優は禁止、などという論議がナンセンスでしかないのは、歴史が教えてくれている。ただ、問題は芝居の内容であるのは言うまでもない。
さて、肝心の『鬼平犯科帳』である。映像でも好評を博している幸四郎だが、過去に祖父・叔父と身内の実績が高く評価されているために、そのプレッシャーは相当なものだろう。古典の歌舞伎作品を継承してゆくのは歌舞伎の世界では当たり前の話でも、「新作歌舞伎」で内容は若干違うものの、主人公が同じ作品を引き継いでゆくのは、例外とも言えるケースだ。先代の鬼平ファンも多い中、プレッシャーも大きかったはずだ。しかし、それを跳ね除けて、「令和の鬼平」を創り上げたのは成功であると同時に、「新作歌舞伎」の今後のありようを提示したとも言える。
二幕構成のこの舞台では、序幕の大部分を、若きの長谷川平蔵を描き、子息の市川染五郎が演じている。序幕に市川團十郎が付き合っているが、いかにも気の入らないお粗末な芝居ぶりだ。娘のぼたんも出演しているのだから、成田屋親子VS高麗屋親子の気概が欲しかった。
序幕の染五郎がいい。今まで、時に線の細さを感じることがあったが、ずいぶんと逞しい芝居を見せるようになった。無頼で、男らしく、何をしてよいのかわからない若者の屈折が暴発するように見えるのは、完全に一回り芝居が大きくなった証拠だ。芝居の角々にもメリハリがあり、旬の若鮎のような香気と勢いがある。僅かの期間に、ずいぶんと芝居の寸法が延びた。若い時期にいろいろな役に挑戦することの意味や、本人の努力が報われたのだろう。
序幕の幕切れには、鬼平の父親で、史実でも「長谷川平蔵」の俗称で呼ばれていた父を白鸚が、現在の鬼平を幸四郎、若き日の鬼平を染五郎が演じる「夢現(ゆめうつつ)」の場面で、親子孫三代の共演だ。短い場面だが、白鸚の力強い台詞と貫録を見せるご馳走、とも言える場面だ。
幸四郎の平蔵、吉右衛門のそれとは違ったユーモアのセンスで、吉右衛門が見せた柔らかな部分も持ち合わせ、剛と情に満ちた鬼平になった。話の筋がわかりやすく、台詞も歌舞伎の古典とは違ってわかりやすい。「新作歌舞伎」の実験があちこちの劇場で盛んなのは結構で、これからの新しい観客を呼び込むために、いろいろな可能性を探ることは必要だ。ただ、漫画やゲームを原作にした作品よりも、過去の優れた時代作品の歌舞伎化が、最もまっとうな方法であることを示した点は大きい。同時に、新作で祖父、叔父と三代にわたって演じられる作品を持った幸四郎の幸福でもあろう。
二本目はがらりと趣向を変え、染五郎、市川團子のコンビによる舞踊『蝶の道行』。この世で添い遂げることが叶わなかった男女が、蝶の精になって美しい踊りを見せる。團子の小槇、染五郎の助国ともに清新な若々しい美しさがある。今までにも多くのコンビが演じてきたもので、それぞれの良さや特徴がある。このコンビは、やはり初々しい美しさに点が入る。
七月の歌舞伎座公演の夜の部は、幸四郎の責任芝居のようなものだが、科白や佇まいを観ていると、加速度的に進む歌舞伎界の世代交代の中で、古典、世話物、舞踊、新作とそれぞれの場で研鑽を積み、歌舞伎の次の世代を担うべき場所に座っているのがよくわかる。今後のさらなる活躍が楽しみだ。