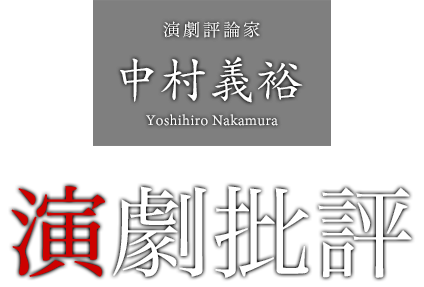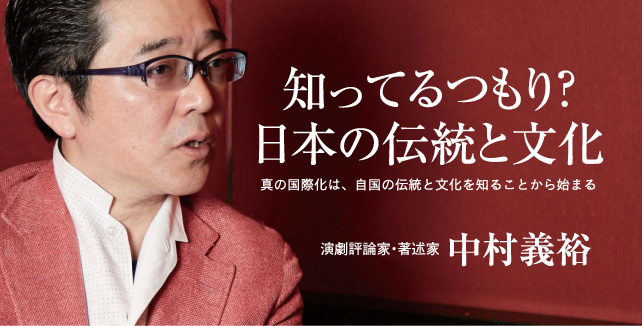2011年の初演以来、今回が4演目となる『滝沢家の内乱』。『南総里見八犬伝』で名高い滝沢馬琴(1767~1848)が、この大長編を執筆中に目を患い執筆が不可能となり、息子の嫁・お路が口述筆記で残りを完成させた、というエピソードは有名だ。そこだけに焦点を当てるのではなく、滝沢馬琴がどのような環境の中で日々を過ごし、歴史に残る名作を書き上げたのか。そこに目を付けた劇作家の吉永仁郎(1929~2022)の佳作とも言える作品だ。馬琴と言えば、日本で初めて原稿料で生計を立てることができた文筆家など、エピソードには事欠かない人物だが、あえて「滝沢家」の内部のみに焦点を当てたところに、作者の劇作家としての優れた眼が光っている。
登場人物は二名だけ。馬琴を演じる加藤健一と、息子の嫁・お路の加藤忍。声だけだが、馬琴の妻・お百を高畑淳子、息子でお路の夫・宗伯を風間杜夫が演じている。姿を見せないこの二人の騒ぎっぷりが、作品のよきアクセントになっている。手練れの劇作家の仕事だ。声のみで芝居をする二人がいることで、滝沢家の様子がより重層的になり、馬琴や時にお路が語る言葉を通して、二人の人物の性格はもちろん、世間や時代の動きまで見えてくる。
江戸時代にある程度の成熟を迎えた「家」制度の中で、家長として文筆だけではなく、果実の栽培や調薬などで何とか暮らしをまとめている馬琴の誇りと頑なさ。その影響か、息子の宗伯は生来の病弱に加えて、ヒステリックな母の言動もあって精神的に追い詰められている。生来の性格で日々刻々、不満の大声を上げる馬琴の妻・お百。有名な馬琴の家に嫁に、との嬉しさで嫁いできたお路は、当初は家族間で世間話さえしない滝沢家の生活に、勝手が違って戸惑うものの、徐々に馴れてゆく。簡単ではないが、「滝沢家」の人間になってゆく中で、馬琴の信頼を得るようになる。目が不自由になった馬琴は、知らぬ間に文字の勉強をしていたお路の熱意に驚きつつも、最後の巻の完成を共に歩むことにする。加えて、お路のやる気と才能を見抜いた馬琴は、自らの筆名の一字を与え、「琴童」の筆名を与え、お路ものちに文筆家となる。嫁と長男に振り回された馬琴の晩年に潤いを与えたのは、息子の嫁だったのだ。
単に、歴史に名を残した人の物語ではなく、時に等身大の姿を描きながら、世間や文学と闘う馬琴の姿を活写した吉永の作品を、ほぼ喋りっぱなしの加藤健一が、気難しいようでいながら情のある男の姿を描いて見せた。
この作品の上演に当たり、加藤自らが演出を担っているが、こんなことを語っていた。「以前の演出は、馬琴の台詞が約七割ということもあり、また、江戸時代の家制度の中で、嫁という立場でそう喋るものではない、と作者の吉永先生は考えておられたのだと思います。台詞の割合は違っても、この芝居は二人が主役なので、そう見えるような演出にしたいと思います」。
確かに、初演の2011年の舞台に比べると、加藤忍が演じるお路は陽気で活発、何事にも前向きな側面がよく出ている。馬琴の夢の中に登場する場面などは、いささかやり過ぎぐらいの感があるものの、それが芝居の中のアクセントにもなっている。充分に、二人主役の期待に応えていると言えよう。馬琴は、考え事や気分転換の折に、一人で屋根に上り、星空を眺めている。それがお路の知るところとなり、いつかお路も一緒に屋根の上に上るようになる。一人の至福の時間を邪魔された苛立ちが、時を経て、二人での何気ない会話を楽しむ時間に変わる馬琴の姿が象徴的である。細部にわたるまで、非常に工夫が凝らされ、よく描かれた脚本である。
ところで、この公演は7月1日の夕刻、「かめありリリオホール」で加藤健一事務所でも初めての試みで「ゲネプロ体験会」の名称で、本番通りに開催された。公演は4日までで、以降は8月半ばまで、長野県を振り出しに岡山、広島、島根、鳥取などの地方公演が続く。
現在の「新劇」と呼ばれる分野のストレート・プレイに共通した問題で、頭を抱えている劇団や事務所は多いが、この分野の演劇を支えてきた層が高齢化やコロナなどの問題で、夜の公演には観客が集まらなくなっている。しかし、昼公演ばかりだと、仕事帰りなどに観劇をすることができない。ここに、現在の演劇が抱える問題の一つがある。ミュージカルなどは夜も昼も関係なく若い観客層が集まるが、こうした、じっくりと芝居を楽しむ公演にはなかなか足を運んでくれない、との問題がある。
今回の公演会場は亀有で、東京都の端っこに近いが、一時間あれば、千葉、神奈川、埼玉、東京、かなりの範囲までの人の観劇対象になる。上演時間も、休憩を挟んで2時間20分と、長い芝居を敬遠しだした最近の傾向におさまる範囲で、9時には終演している。「芝居を観る」ことが、普通の大人の娯楽としてなかなか根付かない問題は、今に始まったことではない。しかし、こうした作品に出会うと「もったいない、こういう楽しみもあるのに…」と思ってしまう。
今は季節が良くないかもしれないが、我々の生活の中で、「演劇」という存在がもう少し大きくならないものか、と切歯扼腕するばかりだ。